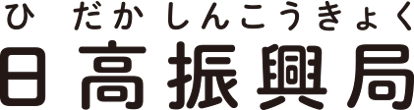令和6年10月30日(水)、次代を担う青年農業者ゼミナール(以下:農ゼミ)第2回研修会として、壮瞥町と洞爺湖町への視察研修を開催しました。
農ゼミ生4名と振興局・普及センターの職員が参加し、施設栽培ナスの環境制御の取組や、有機および特別栽培のミニトマトでの土づくり等を学びました。
病害対策のためヤシガラ培地を使い日射比例かん水・温湿度・二酸化炭素濃度までコントロールする環境制御技術と、堆肥や緑肥、栽培後の残渣も利用して品種を選びながら20年以上有機栽培を行っている技術。まったく違うようで、どちらも植物生理や生産効率、経済性などが深く考慮された持続可能な農業となっていて、学ぶ事が多く、参加者の満足度が高い視察研修となりました。

壮瞥町の環境制御を行っているナス栽培ハウス。
パソコンやスマホでハウス内環境が把握でき、状況に応じて温湿度やかん水等の設定ができることを、参加者がパソコンをのぞき込み確認しています。

洞爺湖町佐伯農園の特別栽培や有機栽培のミニトマト栽培ハウス。
「施設栽培は連作となり土壌の微生物やミネラルのバランスが崩れがち。また土壌に一番良くないのは裸地化していること。短い期間でも緑肥を栽培することで土壌中の生物相が変わり、緑肥の生育状況で土壌状態が把握できる。」など、実績に裏打ちされた土づくりの話を聞くことができました。